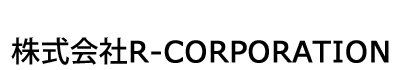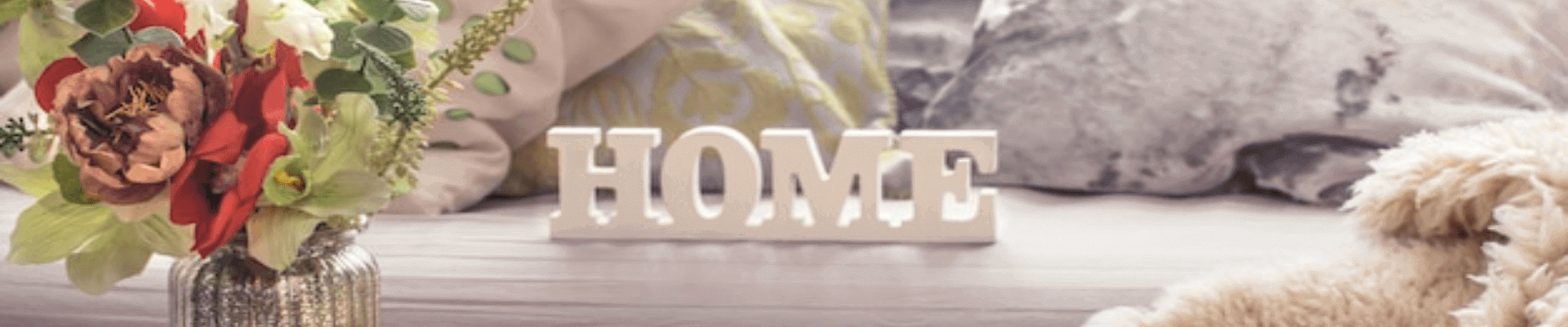
障害者グループホーム第三者評価について
福祉サービスは本来、非常に個別性が高く標準化には馴染まないサービスです。また、福祉サービスの理念が実現されたかどうかを外部から評価することは極めて困難です。なぜなら「尊厳の保持や自己決定の尊重、自己実現の達成」が叶ったかは、サービス提供を受けた利用者本人の「実感」によってでしか確認することができず、かつ「実感」にはその時々の思いや暮らしの環境を背景に著しい個人差があります。
そのため、組織全体で課題を共有して改善していくことを目的に、他分野と共通の6つの「共通評価対象領域」に7つ目の「日常生活支援」を加え、自己評価を重視する評価手法としています。
第三者評価の標準的な手順
❶
契約
スケジュールフロー、必要書類ご郵送
❷
自己評価の実施
「住居単位」で自己評価表を作成
※複数住居を一体的に運営している場合は合同で作成しても可(評価結果は住居ごと)
※サテライト型住居は本体住居に含む形
❸
❹
●訪問調査(調査者2名・1.5日)
サテライト型住居は協議の上訪問有無を決定
●利用者調査(アンケート&ヒアリング調査)
事務所の強み・弱み、評価 60細目当についてヒアリングの下、事実確認
❺
評価結果報告書提出
コンセンサス 7~10日
❻
評価結果の公表:推進機構HP
promise
弊社・調査者は評価調査及び評価結果報告書をまとめる際も、個人情報保護に配慮して作成いたします。
また、事前書類、情報に関する守秘義務を徹底いたします。
基本的視点
1.「障害者グループホームの多様性を尊重」
様々な運営形態や、利用者の障害特性等、サービス提供の体制、支援についての「望ましさ」や「理想の姿」を1つに固定し、こうあるべき、こう対応すべきという一律の尺度を安易に当て実践を求めることは利用者の主体性を尊重した生活を損なうことにつながります。多様性の尊重を大前提とします。
2.「職員の思いを聴く」
職員が外務からの承認や動機付けを得られる機会が多くありません。サービスの質を高める上で職員自身が課題解決や質の向上への動機を持つことが欠かせません。対話形式による調査面接を重視し、職員の「思い」を丁寧に聴くことを重視します。
3.「振り返り重視」
限られた空間で利用者・職員間の密度の濃い人間関係が築かれますが、一方、密室性が高くなり、サービス提供の実態が外部からは見えにくい面があります。特異な勤務体制により、サービス提供が提供する側の視点中心で進められてしまう危険性も高くなります。自己評価の実施により日々のサービス提供をともに振り返り、利用者支援の目標や方針を共有することにつながるよう、取組をバックアップする事を重視します。
Rは自己評価だけでは到達できない振り返りを支援致します。
自己評価の取組
ホーム運営に携わる生活支援、世話人、調理補助員等、全員参加で取り組まれることを期待します。
評価項目
● 共通評価(4カテゴリ・16事項)217項目
● 内容評価(2カテゴリ・10事項)80項目
実施内容
● STEP①
評価項目297項目について個人で◎・〇・△・×の4段評価
● STEP②
STEP①を取りまとめ、ホーム全体で◎・〇・△・×の4段評価
● STEP③
STEP①・②を踏まえ、評価対象等単位(6カテゴリ・26事項)を文章記述
評価基準
国の評価基準ガイドラインに準拠しつつ、神奈川県独自性を継承
評価項目
60細目
共通評価(管理者)45 細目
内容評価(現場)15 細目
自己評価
① 自己評価(各職員)
② 自己評価(ホーム全体)
③ ① ・② の結果を基に現在・将来の取組を一体的に文章で記入(努力・工夫・課題等)
評価調査
1. 事前書面調査
2. 訪問調査(1.5日)
3. 利用者アンケート(全員)
4. 利用者ヒアリング(1名以上)
調査項目
1. 事前書面調査
2. 訪問調査(1.5日)
3. 利用者アンケート(全員)
4. 利用者ヒアリング(1名以上)
公表
Ⅰ. 評価結果報告書
Ⅱ. 第三者評価結果
Ⅲ. 利用者調査結果
非公表
自己評価結果(3)
評価細目の達成度
基本情報・住所以下全て
株式会社R-CORPORATION
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町74-1
大和地所ビル9F
TEL:045-264-6621
FAX:045-264-4746
MAIL:pr@r-corp.jp